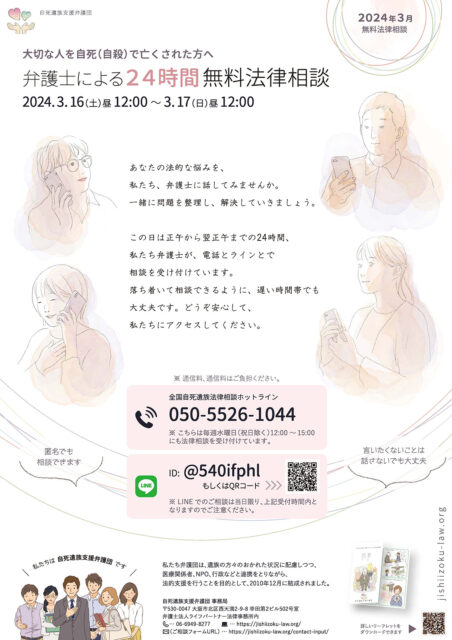弁護士の井上です。
最近、相談数の増加とも相まって、児童・思春期の子どもの自死と精神障害の関係について考えることが多くなりました。
例えば、子どもの自死が起こった場合、学校でいじめがあったのではないか、など分かり易い事象にフォーカスして調査が行われ、その結果、いじめはなかった、あるいは、いじめはあったが軽微なものであったという場合に、自死との因果関係は認められない、という調査報告と共に、自死の真相はわからないままとなってしまうことも少なくないと思います。また、その際、自死との間に精神障害が介在している可能性についてしっかりと検討されることは少ないのではないでしょうか。
しかしながら、今日では、医学的知見の蓄積により、自死には精神障害の影響が深くかかわっていること、子どもも大人と同じように精神障害を発症する場合があること[※1]、については広く知られていますので、私は、自死の原因の一つとしていじめが想定されるケースであろうとなかろうと、子どもの自死事件については、精神障害の発症が介在している可能性を否定すべきではないと考えています。すなわち、子どもの自死が生じた場合、常に「精神的負荷の蓄積→精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを念頭において調査・検討が行われるべきであるということです。
そのようなアプローチで調査・検討がなされる機会が多くなれば、「精神障害の影響による死」、すなわち「病死」であったという「真実」に辿り着けるご遺族も増えるのではないでしょうか。もちろん、精神障害の原因は多岐にわたりますので、原因の調査にもおのずと限界はあります。それでも、「我が子の自死の原因が全く分からない」という状況から解放されるご遺族が増えることを願ってやみません。
また、「精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを考えることは、亡くなった子供が苛烈ないじめに遭っていたというケースにおいても重要であることは言うまでもありません。精神障害の発症が介在した自死と認定されることが増えれば、自死は「基本的には行為者が自らの意思で選択した行為である」とする非科学的な判決[※2]によって傷付けられるご遺族は少なくなると思います。
なお、児童・思春期の精神障害については、2019年5月に発表された「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、これまで成人期における臨床的特徴が周知されている障害が児童思春期に生じた場合にはどのような臨床的特徴を呈するか、という観点に配慮した記載がなされることとなりました。例えば、大人の場合の「抑うつ気分」が、児童思春期の場合は、身体愁訴、分離不安の高まり、イライラなどとして表れることが明記されることとなり[※3]、従来よりも児童思春期における精神障害の診断がしやすくなることが期待されます。
※1神庭重信編(2020)。「講座精神疾患の臨床1 気分症群」中山書店。
※2一例として、大阪高判令和2年2月27日。
※3「精神医学」(2019)第61巻第3号