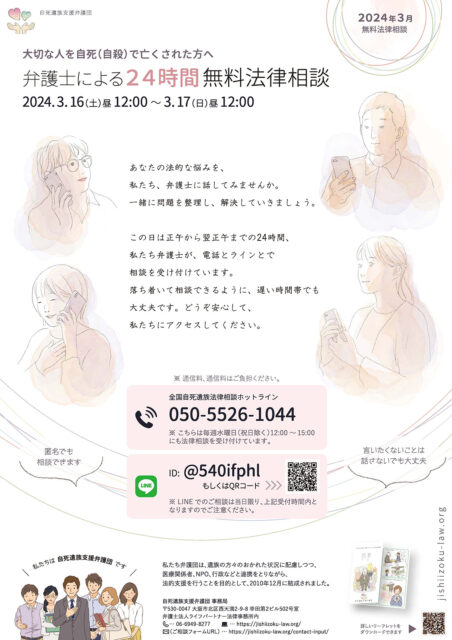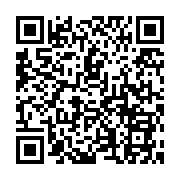1 パワーハラスメントの6類型
過労自殺(自死)や過労うつの労災の認定基準が令和5年9月1日に改訂されました(以下「令和5年認定基準」といいます。)(※1)。
令和5年認定基準は、業務による心理的負荷表(以下「別表1」といいます。)に、以下のパワーハラスメント6類型を組み込んだ点に最大の特徴があります。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
労災実務上、パワーハラスメント6類型が別表1において例示された意義は大きいといえます。
改定前の令和2年認定基準(※2)では、ご遺族が「パワーハラスメントを受けた」という出来事の存在を主張しても、労働基準監督署長は「業務指導の範囲内だからパワーハラスメントではありません。」などと判断し、労災を認めない事例が散見されました。
特に無視等の「人間関係からの切り離し」は、令和2年認定基準に記載すらなかったため軽視される傾向がありました。しかし、無視などの人間関係からの切り離しはとても辛い行為です。例えば、指示を求めても舌打ちをしたりため息をついて無視をする、「こいつは使えない。」などといってメンバーから外す、別の部屋に押し込んでしまうなどの行為は、被害者から見るとこれだけで強いストレスを感じ、職場に行きたくないと思うでしょう。
実際、令和2年に実施されたストレスの強度に関する医学研究でも「上司等から人間関係からの切り離しを受けた」というライフイベントのストレスはとても強かったのです(※3)。
令和5年認定基準は、このような医学研究も踏まえ、無視などの「人間関係からの切り離し」を含む6類型を示しました。少しでも過労自殺(自死)のご遺族の救済が広まればと考えています。
2 労災になるパワーハラスメントの回数や頻度って?
被害者からするとパワーハラスメントは1回でも嫌なものです。では、パワーハラスメントがどれくらいの回数や頻度で行われれば労災として認められるのでしょうか?
令和5年認定基準は、労災として認定されるためにはパワーハラスメントが「反復・継続するなどして執拗」に行われなければならないとしています。
しかし、「反復・継続するなどして執拗」とは具体的にどのような場合なのか分かりにくいですね。
令和5年認定基準は「一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況」を意味するとしていますが、「たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況」も含むとしています。具体的には、パワーハラスメントが1日だけの場合であっても、その1日の中での回数や時間を考慮して、長時間になっている場合や、しつこく繰り返し行われていた場合はこれに当たるとされています。そして、長時間かどうかは、指導のために必要な時間をどれだけ超えているか、どれだけ就労環境が害されたかによって判断するとされています(※4)。
また、「反復・継続」という記載は、反復または継続と解釈すべきでしょう。
実は、令和5年認定基準はセクシュアルハラスメントの場合、「継続」すれば労災として認定します。つまり、セクシュアルハラスメントの場合は「継続」でOKなのに、パワーハラスメントは「反復・継続」じゃないとダメなのです。パワーハラスメントもセクシュアルハラスメントも同じだと思うのですが、皆さんはどう考えますか?
ところで「継続」で足りるという考えは医学的にも裏付けることができます。パワーハラスメントによるストレスは、上司等による直接の言動による急性ストレスと、そのような上司等と職場で過ごさなければならないという慢性ストレスに区別することができます。そして、慢性ストレスが「身体に対して多岐にわたり影響を及ぼし」、「神経、精神疾患においても、うつ病、身体表現性障害や不安障害、てんかん、統合失調症がストレスによって誘発ないしは悪化することも周知の事実」となっています(※5)。つまり、パワーハラスメントを加えるような上司と一緒に職場に居るだけで体と精神を壊してしまうのです。そのことを考えれば、パワーハラスメントが「継続」すれば労災と認めるべきでしょう。
3 助けてもらえない状態は評価される
上司からパワーハラスメントを受けているのに周りが無視したり、会社に対して改善を求めても何もせず逆に指導を受けたり、改善を求めることで「余計なことを言って輪を乱す。」などと言われて人間関係が悪化したら、皆さんはどう感じるでしょうか。私なら「もう嫌だ。ここに居られない。」と感じて会社を辞めるでしょう。
このように、ストレスを受けた際、支援が不足するとストレスが強まることは、医学的にも知られています(※6)。
そこで、令和5年認定基準では、パワーハラスメントだけでは「中」と評価されて労災にならない場合であっても、①「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」、②「会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合」は労災として認定することになりました。
しかし、令和5年認定基準は、セクシュアルハラスメントについては、セクシュアルハラスメントだけでは「中」と評価されて労災にならない場合であっても、①と②に加えて、③「会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した場合」も労災として認定します。ここでも、パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントで差違があるのです。
そもそも、③の場合とは、コミュニケーションがとれなくなれば、パワーハラスメント6類型の「人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)」に該当し得ますし、上司等からの支援の不足は明らかです。
ですので、パワーはラメントも①と②だけではなく、③の場合も労災として認定すべきだと考えます。
※1 令和5年9月1日付「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
※2 令和2年5月29日付「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html
※3 日本産業精神保健学会「令和2年度ストレス評価に関する調査研究報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000863009.pdf
※4 厚生労働省労働局補償課「精神障害の労災認定実務要領【本編】」(令和5年11月)
※5 日本産業精神保健学会「精神疾患と業務関連性に関する検討委員会」「『過労自殺』を巡る精神医学上の問題に係る見解」
http://mhl.or.jp/kenkai.pdf
※6 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」(令和5年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001117056.pdf