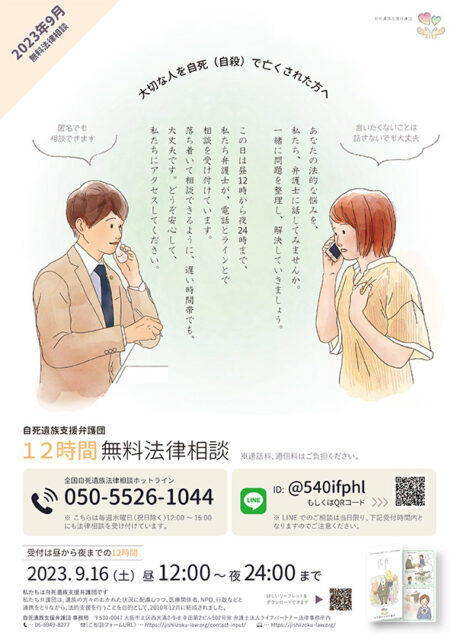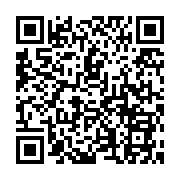近年、著名人の自死に関する報道を目にする機会が増えました。その背景に、インターネット上での誹謗中傷が影響したとみられるケースが後を絶ちません。
主に学校に関連するネット上のいじめやプロバイダ責任制限法の改正については、2023年1月30日付の田中健太郎弁護士のブログ記事(「学校でのネットいじめへの対応」)でも触れているところですが、インターネット上での誹謗中傷がなされた場合の相手方の特定方法と加害者の責任について、あらためて整理したいと思います。
1 加害者の特定方法
(1) 誹謗中傷の加害者(発信者)を特定するためには、①コンテンツプロバイダ(サイトやSNSの運営会社)に対して投稿時のIPアドレス等の開示請求を行い、②開示されたIPアドレス等から利用されたアクセスプロバイダ(NTTなどの通信事業者)を特定し、さらに、③同アクセスプロバイダに対して契約情報の開示請求を行うというプロセスを経る必要があります。
①③について、各プロバイダが裁判外で任意に開示をしない限り、加害者を特定するために2回の裁判手続を経る必要があります。そのため、被害者にとっては多くの時間とコストがかかり負担が大きく、また、開示に時間がかかっているうちにログの消去などで発信者の特定が困難になってしまう場合がある、という課題がありました。
(2) そこで、令和2年及び令和3年に、発信者情報の開示手続を簡易かつ迅速に行うことができるように、プロバイダ責任制限法についていくつかの法改正がなされました。
その一つが、2023年1月30日付の田中健太郎弁護士のブログ記事(「学校でのネットいじめへの対応」)でも触れていた新たな開示手続の運用です。1つの裁判手続で発信者情報を開示できるよう、発信者情報開示命令という非訟手続が新設されたものです。この手続では、基本となる発信者情報開示命令に加え、提供命令(コンテンツプロバイダが有するアクセスプロバイダの名称の提供を命令すること)、消去禁止命令(発信者情報を削除することを禁止すること)という合計3つの命令が組み合わさって進行し、発信者情報の開示を一つの手続で行うことが可能となります。プロバイダ側の協力が前提になりますが、争訟性の低い事案については簡易迅速な情報開示が狙いとされています。
(3) その他の改正のポイントについてもご紹介します。
まず、プロバイダ責任制限法の委任を受けた省令が改正され、「発信者の電話番号」が開示対象となることが明記されました。これにより、手続①でコンテンツプロバイダから投稿者の電話番号の開示を受けた場合、電話会社を特定したうえで弁護士会照会により電話番号の契約者を照会することで投稿者が特定できるようになりました。電話番号の開示を受けることができた場合には、③の手続を省略することができるため、従来よりも時間と費用の負担が軽減され得るものといえます。
また、SNS等の中には、個別の投稿に関する通信記録を保存せず、アカウントへのログイン情報のみを保存する「ログイン型」と呼ばれるものがあります。X(旧Twitter)やFacebook等がこれに当たります。改正前の法では、このようなログイン型が想定されておらず、開示対象となるのは「当該権利の侵害に係る発信者情報」に限られ、ログイン情報が開示の対象となるのか不明確でした。改正法は、ログイン情報の通信に関しても「侵害関連通信」とし、侵害関連情報に係る発信者情報を「特定発信者情報」として、開示対象となることを明確にしました。
ただし、あくまで、権利侵害を伴う通信に関する情報開示が原則であり、ログイン情報の通信からの情報開示については補充的なものとして位置づけられています。そのため、補充的要件が加重され、開示請求できる場合が限定されている点に注意が必要です。このような手続きによって判明した投稿者に対し、損害賠償請求や刑事告訴をしていくことになります。
2 加害者の責任
(1) 刑事責任
インターネット上で誹謗中傷を行った加害者生じる刑事責任には、主に名誉毀損罪、侮辱罪による責任があります。
名誉毀損罪は、不特定多数の第三者に対して、事実を摘示して、人の社会的評価を低下させる行為をしたことで成立する犯罪です。刑法230条により「3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金」に処せられます。
他方、侮辱罪とは、事実を摘示することなく、他人おとしめるような言動をしたことで成立する犯罪です。名誉毀損罪との違いは、事実を摘示しているかどうかという点にあります。
侮辱罪は、従来の法定刑は拘留又は科料でしたが、2022年7月の改正以降は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の法定刑となりました。
侮辱罪の厳罰化には、2020年5月、テレビ番組に出演していた女子プロレスラーがSNS上で誹謗中傷を受け命を絶つ事件が発生した経緯がありました。同事件では、投稿者である2名が侮辱罪で略式手続で起訴されましたが、科された刑罰はいずれも科料9000円にとどまりました。これを受け、侮辱罪の罰則が低すぎるとの指摘がなされ、また、名誉毀損罪の場合と法定刑に差がありすぎたことも踏まえて厳罰化に至りました。
(2) 民事責任
誹謗中傷が民事上の不法行為(民法709条)に当たる場合には、被害者は加害者である投稿者に対して損害賠償請求をすることができます。
誹謗中傷が影響して自死に至ったと思われるケースであっても、裁判で認められ得る慰謝料金額については注意が必要です。誹謗中傷により傷ついたという意味での精神的苦痛に対する慰謝料は、数十万程度となってしまいます。誹謗中傷により自死に追いやられたという死亡慰謝料が認められるためには、加害行為と死亡の結果について法的な因果関係が認められる必要がありますが、誹謗中傷の被害者が必ずしも自殺するわけではなく、自殺することまで予見できたとは限らないことを踏まえると、この因果関係を認めることは難しいのが通常です。
3 まとめ
以上のように、インターネット上の誹謗中傷に関しては、近年社会問題化していることから、加害者の特定手続が整備され、また、従来は見過ごされていたような侮辱罪に当たる書き込みも厳罰化に伴い問題視されやすくなることで、悪質な書き込みを抑止する効果も期待できる方向に向かっているものといえます。とはいえ、今なおインターネット上での誹謗中傷が絶えないことや、民事責任の追及が必ずしも容易ではない現状も踏まえて、今後もこの問題については注視していく必要があるものといえます。